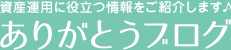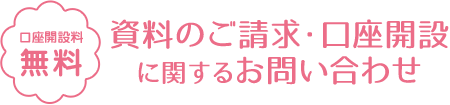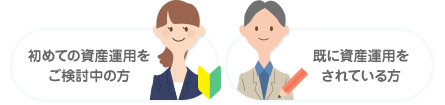ありがとうの本棚(今月の一冊『サラ金の歴史-消費者金融と日本社会 』)
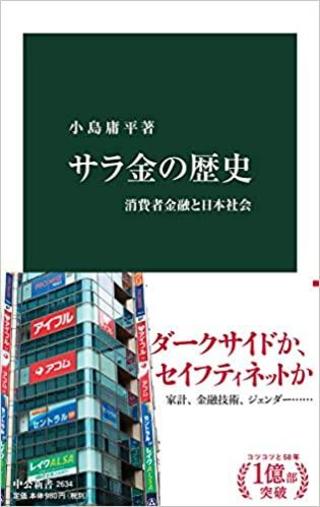
サラ金の歴史-消費者金融と日本社会 (中公新書 2634)新書 - 2021/2/20小島 庸平 (著)
本書はいわゆる消費者金融の発展・拡大・社会問題化・規制強化の歴史を100年前から遡って、その当時の日本社会・経済の状況とともに詳しく解説した本である。
素人高利貸から質屋・月賦、団地金融、サラリーマン金融、消費者金融へと借り手を低所得者や主婦、若者などにも広げながら発展していった歴史がよくわかる。
昨今、金融包摂として、誰でも金融サービスを受けられる世の中にしていこうというSDGs的な動きがあるが、本書を読めばまさにサラ金の歴史こそ金融包摂の歴史であったということが理解できるだろう。
最近では、クレジットカードのリボ払いやキャッシング、カードローン、スマホ完結ローン、BNPL(Buy Now, Pay Later)など、金融技術の進歩とともに、キャッシュレス化が進み、お金を借りていることを意識させない金融サービスが増えて手軽に借りられる便利な世の中になっている。
しかしながら、それは同時に、今までお金を借りられなかった返済能力が低く信用力の低い人達にも高金利でお金を貸し付けるようになったことを意味しており、貸し手が大きな利益を上げる一方で、多重債務者や自殺者、自己破産の増加という負の側面も持ったものであったことを理解しておく必要がある。
成人年齢が18歳に引き下げられて、今年から高校で金融教育が必修化されたが、家計管理とお金の教育の観点から借金するとはどういうことなのかが本書を読めばよくわかる。
大変勉強になるので、特に若い世代に是非読んでもらいたい一冊である。
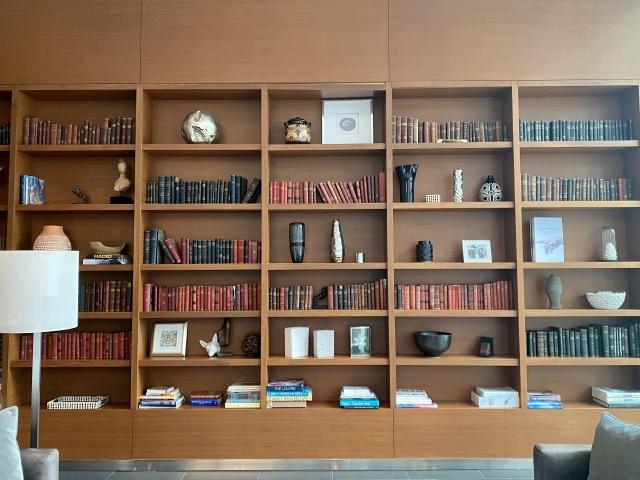
関連記事
| 39コラムTOPへもどる |