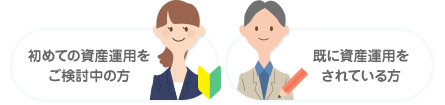【今月のFP情報コラム】「配偶者居住権」で後悔しないために【前編】(2023年3月)

今回のFPコラムでは2020年4月1日施行の改正民法により創設された「配偶者居住権」について、その概要や利用を検討すべきケース、デメリットなども交えて解説します。
「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が、亡くなった配偶者と一緒に住んでいた家に、亡くなるまで居住し続けることを認めた権利です。
社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから,残された配偶者の生活が長期に渡ることも多くなりました。その際には、配偶者が老後の生活資金として預貯金等の資産を確保し、長年住み慣れた我が家で暮らしたいと希望するは当然のことでしょう。
では、なぜ、配偶者居住権という制度ができたのでしょうか。
その理由を具体例で見ていきましょう。
具体例
〈被相続人〉 夫
〈相続人〉 妻・長男・長女
〈相続資産〉 自宅土地建物 6,000万円
預貯金 4,000万円
上記のケースでは夫の遺言書がなければ妻、長男及び長女の3人で遺産分割することになります。妻は全体の2分の1の5,000万円を、子はそれぞれ2,500万円を相続することが、遺産分割協議で決定したとします。妻の法定相続分は5,000万円ですが、6,000万円の自宅を単独で相続すると1,000万円多くなってしまいます。この1,000万円をお金で清算するために長男と長女にそれぞれ500万円ずつ代償金を支払わなければなりません。
妻に1,000万円の資金があり、子に代償金を支払えれば、自宅を単独で相続できますが、そうすると妻の老後資金が不足する恐れがあります。
もっと厳しいケースだと、妻に代償金1,000万円の資金がなく、自宅を単独で相続できないケースです。代償金を支払うためには、最悪の場合、自宅を売却しなければいけなくなるかもしれません。そうなると、妻は長年住み慣れた家を出ていかなければならなくなります。
「家族なのだから、話し合って母親が住めるようにしたらいいのに...」と思われる方もいるでしょう。しかし、相続では家族仲が悪い、子供たちは自宅を売却してお金が欲しい、母親が実の母ではなく後妻であるなど...様々な理由からこうした事態が起きてしまうのです。
そこで、このような事態が起こらないようにするために、「配偶者居住権」が創設されました。
活用例
では、「配偶者居住権」を活用した場合を見てみましょう。
まず、自宅の権利を「配偶者居住権(住む権利)」と「負担付き所有権」に分けます。上記の例で自宅6,000万円を「配偶者居住権3,000万円」と「居住権付き所有権3,000万円」とに相続税評価額が計算(実際の相続税評価は配偶者の平均余命と建物の残存耐用年数などを勘案して計算)されたとし、遺産分割協議により居住権は配偶者である妻が相続し、居住権付き所有権は子2人が所有したとします。
配偶者が受け取る遺産は、配偶者居住権3,000万円分+金融資産2,000万円となります。一方で長男と長女は、配偶者居住権による自宅の負担付所有権、つまり居住する権利のない自宅所有権1,500万円+金融資産1,000万円をそれぞれ受け取ることになります。
妻が配偶者居住権を取得することによって、死亡するまではその家に住み続けられ、預貯金も受け取れ、代償金を支払わずに済むか、少なくて済むということになります。
(後編へ続く)
関連記事
| FP・資産形成TOPへもどる |